最新ITを活用した製造業をはじめとするエンタープライズの将来像とはどんな姿か。富士通のCTOが描いた「2030年のエンタープライズの世界」から探ってみたい。
最新ITを活用したエンタープライズの将来はどんな姿なのか。富士通が2024年9月10日に開催した投資家・アナリスト向けのイベント「IR Day 2024」で、執行役員副社長でCTO(最高技術責任者)とCPO(最高製品責任者)を務めるヴィヴェック・マハジャン氏が、同社のテクノロジー戦略とともに、「2030年のエンタープライズの世界」としてAIエージェントによる製造業でのイノベーションを例示して見せた。その話が興味深かったので、今回はその内容を紹介し、エンタープライズの将来像を探ってみたい。同イベントでは、富士通の主力事業であるサービスソリューション分野から「モダナイゼーション」「Fujitsu...
エンタープライズのAIニーズを支えるコンピューティングについても改めて紹介しておこう。マハジャン氏は図3を示しながら、同社のエンタープライズ向けAIコンピューティング基盤の特徴として「省エネ」「ハイコストパフォーマンス」「オープンアーキテクチャ」の3つを挙げた。量子コンピューティングの研究開発にも注力し、グローバル市場でも存在感を発揮している(図3左下)。マハジャン氏は以上のように同社のテクノロジー戦略を紹介した上で、2030年のエンタープライズの世界としてAIエージェントによる製造業でのイノベーションの例について、まず全体像を図4に示し、「2030年にはAIエージェントがエンタープライズの世界で大きな役割を果たしているだろう。狙いは、意思決定のスピードアップと生産性の向上だ。こうした動きが経済に大きなインパクトをもたらすことになる」と述べた。図4は、AIがクロスインダストリーを超えて自律的に最適化や調整、判断する世界として、製造業のサプライチェーンにおける利用イメージを描いたものだ。この図4を全体の構図として、同氏は2030年のエンタープライズの世界でどのようなことが起きるのかを、以
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
 アクセンチュアの提言から考察 「DXから全社変革に向けたCFOの役割」とは?:Weekly Memo(1/2 ページ)DXと表裏一体の企業変革に向けたCFOの役割とは何か。期待以上の成果を生み出しているCFOとそうではないCFOの違いとは。アクセンチュアが発表した調査結果と提言から考察する。
アクセンチュアの提言から考察 「DXから全社変革に向けたCFOの役割」とは?:Weekly Memo(1/2 ページ)DXと表裏一体の企業変革に向けたCFOの役割とは何か。期待以上の成果を生み出しているCFOとそうではないCFOの違いとは。アクセンチュアが発表した調査結果と提言から考察する。
Read more »
 ビジネス変革のためにAIをどう活用する? IBMが説く「3つの視点と7つの変革領域」:Weekly Memo(1/2 ページ)ビジネス変革のためにAIをどう活用すればよいのか。この疑問に対し、日本IBMが新たなAIソリューションを発表した。ユーザーの視点からも興味深い内容だと感じたので、IBMの顧客事例を紹介しつつ解説する。
ビジネス変革のためにAIをどう活用する? IBMが説く「3つの視点と7つの変革領域」:Weekly Memo(1/2 ページ)ビジネス変革のためにAIをどう活用すればよいのか。この疑問に対し、日本IBMが新たなAIソリューションを発表した。ユーザーの視点からも興味深い内容だと感じたので、IBMの顧客事例を紹介しつつ解説する。
Read more »
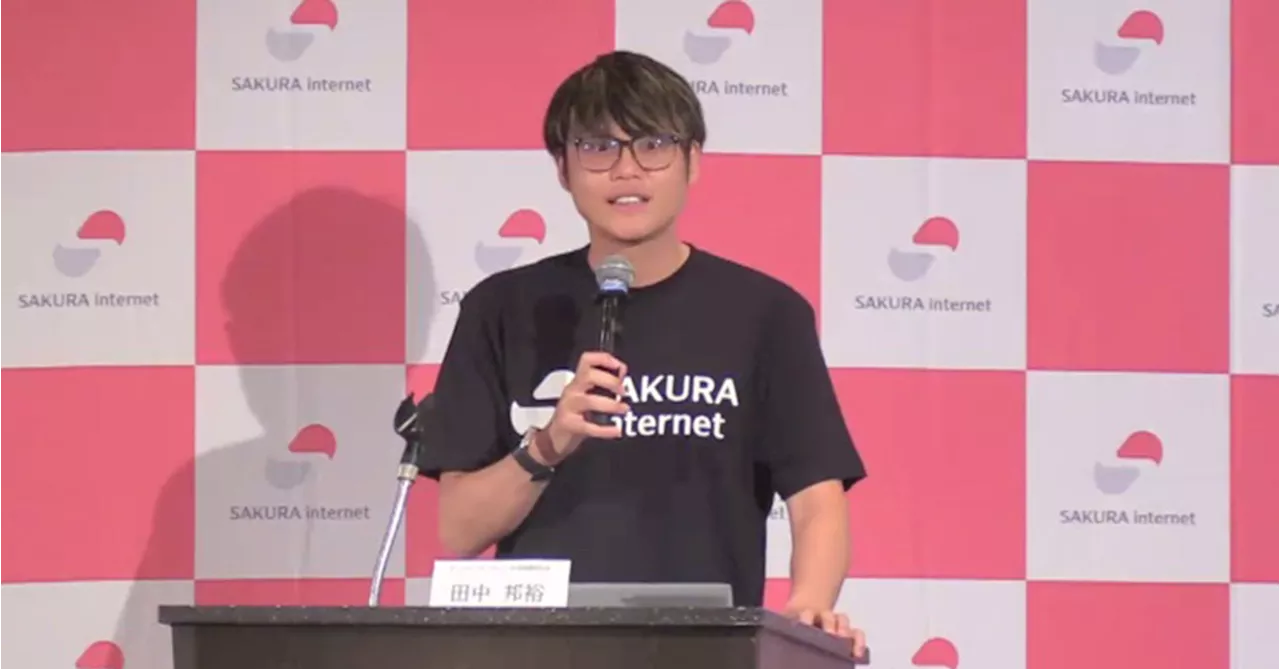 さくらインターネットの取り組みから探る 日本企業は「デジタル赤字」にどう対応すべきか:Weekly Memo(1/2 ページ)日本企業は膨らみ続ける「デジタル赤字」をどう捉え、どのように対応していけばよいのか。政府からガバメントクラウドに指名されたさくらインターネットの取り組みから探る。
さくらインターネットの取り組みから探る 日本企業は「デジタル赤字」にどう対応すべきか:Weekly Memo(1/2 ページ)日本企業は膨らみ続ける「デジタル赤字」をどう捉え、どのように対応していけばよいのか。政府からガバメントクラウドに指名されたさくらインターネットの取り組みから探る。
Read more »
 世界に羽ばたく日本のアニメ・マンガ 躍進の背景と忍び寄る“危機”とは:まつもとあつしの「アニメノミライ」(1/2 ページ)日本のアニメとマンガは国内外で人気を集め、その市場規模は3兆円に迫ろうとしている。一方で10年以上前から低賃金・長時間労働が指摘され、海外大手配信事業者に「安く買いたたかれている」という指摘もある。果たして日本のアニメ・マンガは国を支える基幹産業となれるのか。
世界に羽ばたく日本のアニメ・マンガ 躍進の背景と忍び寄る“危機”とは:まつもとあつしの「アニメノミライ」(1/2 ページ)日本のアニメとマンガは国内外で人気を集め、その市場規模は3兆円に迫ろうとしている。一方で10年以上前から低賃金・長時間労働が指摘され、海外大手配信事業者に「安く買いたたかれている」という指摘もある。果たして日本のアニメ・マンガは国を支える基幹産業となれるのか。
Read more »
 “AIキャラクターによるゲーム実況”の裏側 バンダイナムコ研究所が解説 AI生成コンテンツの“5つの落とし穴”とは:CEDEC 2024(1/3 ページ)バンダイナムコ研究所は、ゲーム開発者向けカンファレンス「CEDEC 2024」に登壇し、AI生成コンテンツの利用例について解説した。AIを活用したゲーム実況配信とゲーム内テキスト生成の2つの領域を主に紹介した。
“AIキャラクターによるゲーム実況”の裏側 バンダイナムコ研究所が解説 AI生成コンテンツの“5つの落とし穴”とは:CEDEC 2024(1/3 ページ)バンダイナムコ研究所は、ゲーム開発者向けカンファレンス「CEDEC 2024」に登壇し、AI生成コンテンツの利用例について解説した。AIを活用したゲーム実況配信とゲーム内テキスト生成の2つの領域を主に紹介した。
Read more »
 日立の「人手不足を生成AIで解消する」発言から改めて問う、“何のために生成AIを使うのか?”:Weekly Memo(1/2 ページ)生成AIを導入する企業が増えてきたが、使用目的がはっきりしないまま動き出しているところも多い。何のために生成AIを使うのか。日立の取り組みから改めて考える。
日立の「人手不足を生成AIで解消する」発言から改めて問う、“何のために生成AIを使うのか?”:Weekly Memo(1/2 ページ)生成AIを導入する企業が増えてきたが、使用目的がはっきりしないまま動き出しているところも多い。何のために生成AIを使うのか。日立の取り組みから改めて考える。
Read more »
